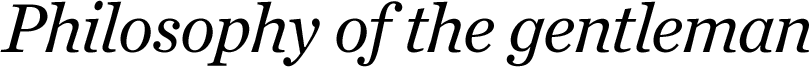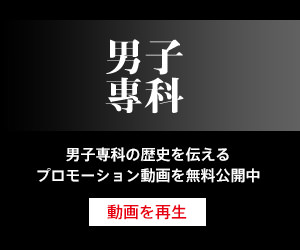2018年チェルシ―フラワーショー アーティザンガーデン(職人の技)部門 金メダルとベストガーデン賞のW受賞をした「おもてなしの庭」
2018年チェルシ―フラワーショー アーティザンガーデン(職人の技)部門 金メダルとベストガーデン賞のW受賞をした「おもてなしの庭」
<花と緑で世界中の人を笑顔に>
庭園デザイナーの石原和幸さんと話をしていると、花にまつわる様々なシーンを思い出す。私が小学生の時、朝、学校に行く前に、玄関で母から渡された花。それは庭から切ってきた紫陽花だったり、週末のハイキングで摘んだアザミだったり、身の回りにある植物ばかりだ。学校に持っていくと先生はとても嬉しそうに受け取り教室に活けてくれた。その頃、花は日常生活の中に溶け込んでいた。
「花と緑で、世界中の人が笑顔になることを目指している」石原さんは、英国で毎年開かれる世界最大の庭と花の祭典「チェルシー・フラワーショー」に13回出場し、10個の金メダルを獲得している世界屈指の庭園デザイナーだ。「この業界でトップであることは間違いありませんが、ここからがスタートです」(石原氏)。
この祭典は英国王立園芸協会が主催し、エリザベス女王が総裁を務め、世界で最も権威があるガーデニングショーとして世界中からトップガーデナーが集まってくる。論文などの書類選考が行われ、それを通過すると出場枠が与えられる。制作期間は9日間、会期は5日間。一人ひとりがプライドをかけて、それぞれの個性、アイデア、想いを詰めこんだ庭の世界を披露する。1万円弱の入場料を支払った世界中から20万人もの人が押しかける。英国人はこのショーを、庭を、心から愛し、ここで見た庭を参考に暮らしに取り入れ人生を楽しんでいる。エリザベス女王から「緑の魔術師」と言われる石原さんの作品は、見る人の心に響く。「見た瞬間に泣く人がいます」(石原氏)と言うほどである。
 エリザベス女王から「あなたは緑の魔術師ね」という言葉を頂いた
エリザベス女王から「あなたは緑の魔術師ね」という言葉を頂いた
2018年チェルシ―フラワーショーで、ポール・スミス氏と
ファッションデザイナー、ポール・スミスとの出会いも、その会場でだった。「ふらっと僕の庭に来て、自己紹介されて、それから毎年見にきてくれて、日本に来ると電話がかかってきますよ。彼のデザインのもとはチェルシ―・フラワーショーですし、僕のシリーズもあるんです」(石原氏)。インタビュー当日も、2018年に金メダルを獲得した時に着ていたポール・スミスの服を着てくださった。
チェルシ―フラワーショーに押し寄せる人
<路上花屋から世界のトップへ>
石原さんは、中学からモトクロスのライダーとして活躍していたが、大学では交通機械工学を専攻し、自動車販売会社で整備士となった。社会人になって、実家でつくり始めた出荷用花の販売の役に立てればと生け花を習い始めたら虜になり、花に人生をかけようと退職。23歳で会社近くの路上販売の花屋でアルバイトを始め、その後、色々な花屋を転々として29歳で独立。「花を売らずに夢を売り」長崎で一番の花屋になる。九州に30店舗を構えるようになった35歳から、依頼されて庭も作っていたが、40歳を過ぎて声をかけられたフランチャイズビジネスで失敗して8億円の負債を追う。借金を返済し続ける中、心が擦り切れそうな時に出会ったのが世界で最も権威あるガーデニングショー「チェルシ―・フラワーショー」であった。
「自分も世界の舞台に挑んでみたい。世界一になれば、すべてがうまくいくはずだ」と挑戦することにした。自分を信じて決死の覚悟で突き進み、初年度シルバーギルトを獲得。その後も挑み続け、世界一の座を手に入れ続けている。
私がおめにかかった日は、2018年のショーが終わったばかりだったのだが、来年のデザインとコンセプトをすぐにでも出さなくてはいけないと言う。なぜ、その庭が世の中に必要なのかを毎日考え、渡航費、滞在費、制作費など1億円の資金をため、英国で準備する3ヵ月休みをとるため必死で仕事をし、ついてきてくれる左官や大工さんなど40人の職人さんたちの人生を丸ごと引き受ける覚悟で臨んでいる。
宝物はいつも持ち歩いているお父様の十字架。「親父は隠れキリシタンでものすごく貧しかったけど、笑顔で仲良く暮らせたらいいねってカッコよかったですね」
<日本の本当の文化は庭造りにある>
いまでこそ、英国が庭園づくりの本場だが「江戸時代、実は日本は、世界一庭師の多い国だったんですよ。280年間戦争がなくて文化はてっぺんにいってたし、絵画も盆栽も庭造りも極まりました。日本の本当の文化は庭造りであり、庭師です。今、英国のガーデニングは4兆円マーケットですが日本では2300億円。高齢化社会になってディズニーランドを超えるような、予約制・会員制でしか見られないような集客力のある庭を造るといったようなことを考えないと、せっかくの日本文化が廃れてしまいます。また男の選択肢として盆栽を持っているとか、いい庭があるとか、庭師を抱えているというのがステキな男だと思うんです」(石原氏)。
そのためにも、庭師が認められる職業になり、稼げる仕事にならないといけないと考えている。庭園デザイナーの地位をあげるには、作品を極める以外にないと懸命だ。
「ビル・ゲイツが『絶対にあいつに頼みたい』という男になりたい」という夢を持つ石原さんの現在の仕事のひとつに、2019年の北京園芸博覧会にチェルシ―・フラワーショーで金賞を受賞した「桃源郷」をつくることがあげられる。後に国営公園として永久展示されることになっているそうだ。飛行機に乗らない日がないほど、世界の現場を飛び回る。
庭はつくった後のメンテナンスがたいへんなのではと伺うと「その発想がダサいんです」と一蹴された。「メンテをやるから価値が上がるんです。庭は出来上がった時点がスタートで、年数を経るごとに良くなっていきます。風景は変わらなくてはなりません。進化させ続けることが、何度も足を運んでくれることだから」。
たしかに名園と言われる庭は敷地の随所に仕掛けがあり、四季折々楽しめるようになっている。手入れをしてこそ、美しさが持続する。
「良い庭は、目だけでなく音、におい、光、手触りと五感で感じられ、わくわくドキドキ感があり人を楽しませることができる。人生一回や。徹底的にやります」(石原氏)。花や木々を眺め、癒され、元気をもらい、命を感じる瞬間を取り戻すためにも、庭を愛で、手をかける余裕を日々の生活の中で取り戻したい。
そしてさらに「サグラダ・ファミリアと並ぶような世界中から見に来るような庭を紛争地域に造れば、雇用が生まれ争いがなくなるのではないか。銃を花の苗に持ち替えてもらう」(石原氏)そんなことを本気で考えている。
「ぼくについてきてくれる職人たちの面倒を一生みにゃいかんから、皆で住める老人ホームの土地を長崎で買いました。そこに庭を造って、その庭を観るために入場料を払って外から入れるようにして、その入場料で運営費をまかないます」(石原氏)。
「お客さんを喜ばせ、驚かせたい」と考え続ける石原さんは「仲間を守る」かっこいい男なのだ。
ウェスティンホテル東京 石原さんの庭は、細部にこだわり、生け花感覚で10センチ単位で仕上げていく
羽田空港第一旅客ターミナルビルの庭には、チェルシ―フラワーショーでシルバーギルトを受賞した「花の楽園」を再現
文:岩崎由美 撮影:木村咲
URL:www.kaza-hana.jp
Instagram:kazuyuki.ishihara